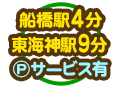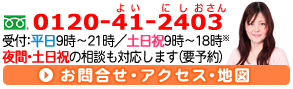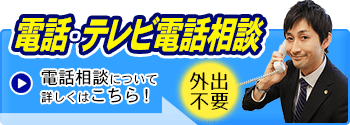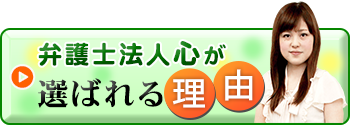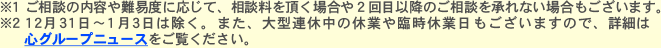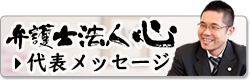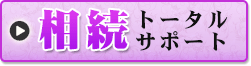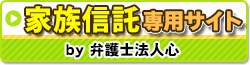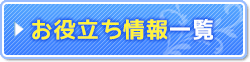自筆証書遺言を作成する際の注意点
1 自筆証書遺言は手軽に作成できるが注意すべき点も多い
自筆証書遺言は、遺言者ご自身が、原則として自筆で作成する遺言です。
紙とペンと印鑑さえあれば、ご自宅等でも気軽に作成できるという利点があります。
もっとも、気軽に作成できる反面、注意すべき点も多く存在します。
代表的な注意点としては、①要件を満たしていないと無効になる可能性があること、②紛失・汚損や、相続開始後に相続人が見つけられない可能性があること、③相続開始後に検認手続きが必要になること等が挙げられます。
以下、注意すべき点について、それぞれ詳しく解説します。
2 要件を満たしていないと無効になる可能性がある
自筆証書遺言は、法律により、形式的な要件が厳格に定められています。
まず、全文を自筆で書く必要があります。
財産目録のみ、ワープロ等を使うことができますが、書面に遺言者の署名押印が必要となります。
次に、作成した日付も正確に記載する必要があります。
最後に、遺言者の署名と押印が必要になります。
押印は認印でも使用可能ですが、同じ苗字の方による偽造が疑われることを防止するため、実印を使用した方が安全です。
3 紛失・汚損や、相続開始後に相続人が見つけられない可能性がある
自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、原本を遺言者ご自身で管理する必要があります。
遺言を紛失または汚損してしまったり、相続開始後に相続人が遺言を見つけられなくなってしまうこと防止するためには、信頼できる親族や、弁護士等の専門家に預ける等の対策が必要です
法務局に自筆証書遺言を預けることも有効ですが、法務局に預けたことを、信頼できる方に伝えておくことが大切です。
4 相続開始後に検認手続きが必要になること
自筆証書遺言は、相続が開始したら、原則として家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
検認とは、裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。
検認の申立てをするには、戸籍謄本類等の資料を収集し、裁判所へ所定の書類を提出する必要があります。
検認を済ませた遺言書がないと、不動産の登記や預貯金の解約・払戻しなどをすることができません。
なお、法務局に自筆証書遺言を預けた場合には検認が不要となります。